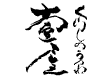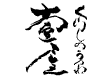青天の霹靂。2024年の幕開けがこんな言葉で始まるとは誰が想像できたでしょう。阪神淡路の経験から、東日本の時も熊本の折も『頑張りすぎないでください』という言葉を店主は掛けてきました。長丁場になります、頑張りすぎると続きません、どうぞ自身の歩幅で歩んでください。
そんな2024年、一所懸命また新たな作品を生み出すことに前進している作り手の展覧が3月に迫ってきました。前回の箸置きの展覧終わりに、次は「たたらでの、唐津焼の鉢や向付を皆様に観ていただきたいと思っているのですが?」と声を掛けてから丸2年。想像以上の難関であったようです。織部焼を中心に、瀬戸・美濃陶で数多く制作されてきた変わり向付。洲浜や扇・輪花に菱形・果ては蛤形から瓢箪形などなど、数多くの向付が作られてきた日本陶磁文化の多様性。唐津焼でも前例があるにはありますが、その土の性質上変形させることの難しさは、想像以上のようです。粘り気の少ない唐津の土は焼成により独特の雰囲気を醸し出し、上品な中にも野趣溢れる仕上がりは、好事家を虜にしてきました。そんな雰囲気をもった多種多様な鉢や向付で一献と洒落込んでみたいとの発想からの店主の無理な願い。
二つ返事で、取り組むことを約束してくれた眞清水藏六。苦難の道が想像できるだけに、感謝の気持ちは言葉では言い表せないものがありました。それから2年、やはり想像以上の難しさや困難にぶち当たったようで、最終的に展覧会の題目も「たたら」という大きなくくりになりました。
還暦を過ぎ、守りに入りがちになる齢(よわい)。唐津にも一歩一歩自分の歩幅で少しでも前へ前へと歩んでいるものづくりがいます。どうか皆様、無理せず一歩一歩歩んでください、その先には今まで見たことも想像したこともない景色がきっと待っていると思います。
『着々寸進 洋々万里』 |