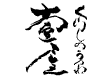|
|||||||||||||||
|
4年振り4回目となる個展の開催(2017年4月)がようやく決まった。ここ数年、幾度となく同じフレーズを携えて丹波路を走った。ある日は石屋川の染井吉野を愛でながら、またある時は六甲の蝉の大合掌を背に、三田フラワータウンの銀杏並木が金色に輝く日もあった。そして昨年末、片口展の報告も兼ねて伺った小雪まじりの立杭の地でその茶碗が産声をあげていた。 今回掲載した柿の蔕茶碗である。「ようやくこんなんができたわぁ。」いつものハニカミ混りの笑顔で出されたひと碗。二代信水という宿命を背負って、日々格闘してきたひとつの答えを感じずにはおれないひと碗。柿の蔕といえば、「青柿」(五島美術館)「京極」(徳川美術館)「白雨」(松永記念館)「大津」(藤田美術館)そして「毘沙門堂」(畠山美術館)などなど名碗が数多く存在する。どの名碗ともどこか違う、そこにはまぎれもない丹波の土から生み出された高麗の雰囲気が匂いたつ茶碗、まさにこれが待ちに待った二代信水の新境地である。 「丹波立杭の陶土をもう一度いちから見直し、さらに南蛮風の焼きの可能性も試してみようと思うんやけど・・・」。そこからは、堰を切ったようにトントン拍子で話が進んだ。さて、その結果をどんな展覧に仕立ててくるのか。柿の蔕を皮切りに、南蛮縄簾・・・ハンネラ・・・、と店主の想いは膨らむ一方である。 4年前の個展終わりに、「次は二代信水としての新境地でお願いします。」と約束を取り付けてからの歳月。気が付くと彼も今年11月には還暦を迎えるという。まさに初心に帰った第一歩を共に歩める今展、期待に胸が膨らむ。 |
|
3年振り3回目となる市野信水展(2013年5月開催)が間近に迫ってきた。今回は今までと全く異にするテーマを彼にぶつけてみた。 過去のこの項でも触れたが、丹波立杭の地は京都にも地理的に近く、時代時代の流行の影響を受け、色とりどりの釉薬や様々な技法が伝わり、それが伝統となって各作り手が多種多様のやきものを作る里として今日の盛隆を見せている。そんな彼の地で、二代信水として伝統的な焼締を中心に作陶に勤しんできた彼に今回「釉薬作品を中心テーマにした展覧で。」とお願いをした。 つい先日、DM用にと3点の画像を持ち込んできた。そこに写っていた作品は、今回掲載の「丹波黒釉水指」と、同じく黒釉の「茶入」、そしてこれから漆蓋を仕立てるという「粉引水指」であった。本名・克明の時代から、黄伊羅保や刷毛目掛分の茶碗などにも定評のある彼が、二代信水として今回のテーマを快諾して取り組んでいる新しい世界。今までコツコツと研究し積み上げてきた丹波の鉄分を多く含む土と相性のいい釉薬に、今回新たに独自の調合による織部釉などの研究成果も披露すべく取り組んでいるという。果たしてどんな結果を出し、どんな作品で挑んでくるのか。 帰り際に一言「焼締も少し出そうかな?全体の雰囲気が締まるし。」との呟きに、取り組んでいる釉薬作品に対する確かな手ごたえと、焼締陶に対する自信が見え隠れした。 開催までに、まだ数回の窯焚きをするという今回の展覧。更なる高みを目指し、新たなものに挑戦するものづくりの姿勢とその成果をご覧いただけると思います。どうぞお楽しみに。 |
|
寸法をご覧いただければお解かりでしょうが、高さ8寸5分に満たない小さな壺である。にもかかわらず、作品から受ける印象は、非常に大きく大らかだ。古丹波の壺を彷彿とさせるものではなく、かといって灰の雰囲気から醸し出される古備前のそれでもない。信楽や越前あるいは瀬戸や常滑に見られる造形でもなければ、李朝のそれとも異にする。 この壺を一目見た時からその印象は不思議と変らない。静かで凛とした佇まいの中に、堂々とした風情を持ち合わせ、なにより優美で健康的である。過去に見た信水作の壺の多くは、古丹波を思わせる肩の張った造形に、灰釉がビードロ状に幾筋も流れた、力強い印象のものであった。今回の壺は、自然灰が肩にしっとり降り、備前の黄胡麻の如き景色があらわれている、これもこの壺の印象を奥深いものにしている。 「壺中の天地」(あるいは「壺中の天」)と後漢の故事にも書かれている、別天地があるとされる壺の中。まさに、この喩えがピタリとくる今回の壺。壺の中にあるという桃源郷を一目覗いてみたいと思わせる。 「壺」には作り手それぞれの思い入れや考え方、ひいては生き方が如実に現れる。荒々しく必要以上に無粋な力感に溢れる壺、また正反対に何とも脆弱で線の細い壺。全体を歪めた壺、口辺を変にいじった壺、不自然に伐ったり千切ったりした壺。もちろん、それらすべてを否定するつもりも批判するつもりもない。ただ、人工的ないき過ぎた造作の中には、桃源郷は存在しないと思う。皆が憧れ最後に行き着く夢の郷とは、人生における苦難苦闘あるいは諸行無常を乗り越えた先にはじめて辿りつく境地にあるのではないだろうか。 壺中の天を拝みたくなる壺には、そうそうお目にかかれない。 |
|
西に法道仙人の開山といわれる和田寺山(わでんじさん)、東に近年はハイキング登山が盛んな虚空蔵山(こくぞうさん)という、標高600メートル足らずの里山の山懐にその地はある。その地所には、南北約3キロ・東西の平坦地に至っては1キロにも満たないにもかかわらず、60を超える窯元が肩を寄せ合って存在している。その和田寺山の東斜面に彼の窯は存在する。県道292号線に面する彼の窯からは、丹波黒豆の刈り取りが終わった畑越しに、虚空蔵山をバックに兵庫陶芸美術館が夕日に照らされ美しく光る。 三本峠を越え下立杭から292号を北上し彼の窯へ向かう道中、いつも何故か同じ光景が彼方の匂いの記憶とともに脳裏をよぎる。学校帰りのランドセルを玄関先に放り投げ、刈り取りの終わった畑へ三々五々集まる悪がきの面々。どこで誰が調達してきたのか、ちょうどいい長さの棒っきれと日によって違う色の球。ベースサイズのベニヤ板の切れっ端が3つ。もちろんグローブなどない。日暮れのカラスの合唱に呼応するかのように必ず誰かが泣きべそをかき始める、これも球と同じで日替わりである。家路につく道端では、仕事を終えた職人さんが軒先の手洗いで顔を洗い、背中に子供をおぶったおっかさん達が夕餉の支度に精を出している。薪の爆ぜる音、夕餉の匂い、風呂場から聞こえる親子の声と湯気に混じる石鹸の香り。皆が知人であり、寄り添って生きている。 そんな「昭和」の原風景が残っている立杭の地で、心のこもったやきものを作っている彼、市野信水。彼はこの地で生まれこの地で土に帰るのである。その営みの奥行き、そして健康で健全な姿。そんなものが、うつわに宿るという基本的な事さえ忘れかけている今のものづくり。不健康な思考や精神からは、決して連綿と使い続けられるものは生まれない。この単純でありながら重要な要素を、現代社会で実践することの難しさが少し解かってきたような気がする。だから、今回の個展のDM写真は、そんな彼の窯場で撮ってみた。彼は健康である。 |
|
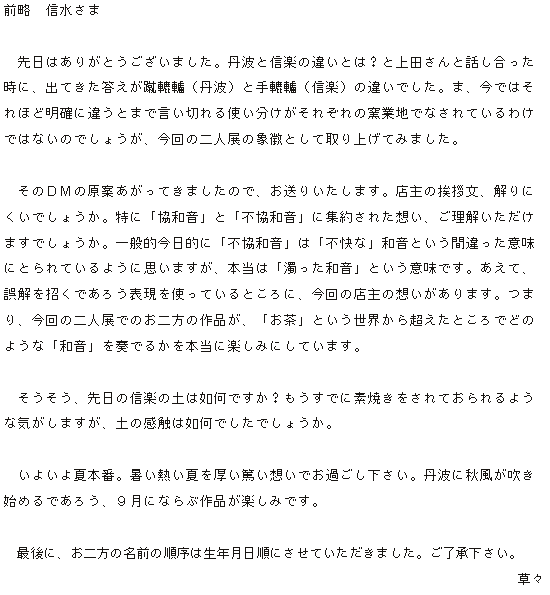
|
|
丹波焼の不思議。日本六古窯に数えられるその歴史の始まりは、昭和52年三本峠北窯の物原の発掘調査から平安末期とされている一方、別地域での須恵器の発見(水谷地区など)もあり定まっていない現状がある。また、窯も桃山期までの穴窯焼成の時代を経て、秀吉の朝鮮出兵後は半地下式登り窯焼成に移行していくと同時に、左回りの蹴り轆轤という日本では珍しい技術も導入された。江戸期以降の変遷も興味深く、小堀遠州の影響で茶陶がその中心に位置した時代を経て、生活雑器へと移行していく。さらに昭和に入ると、柳宗悦・バーナードリーチなどの影響を受け民芸陶が盛んに作られる一方、同時期に北大路魯山人などの来訪を受け「古丹波」の復刻にも時代の波が押し寄せた。また、名称についても不思議で、穴窯時代は「小野原焼」、登り窯の時代に入ると「丹波焼」または「立杭焼」、果ては昭和53年には伝統工芸品指定名称として「丹波立杭焼」と呼ばれ始める。 |
|
今年のゴールデンウィーク期間中、休廊させていただいた。名古屋を皮切り に都心まで10数箇所の美術館を巡る旅を終え、この原稿を書いている。 中でも、愛知万博記念特別企画『桃山陶の華麗な世界』と銘打った愛知県陶磁資料館での印象はこの世界で生きる人間の一人として、考えさせられることが多かった。 4月30日朝9時前に美術館に到着(現在は予約なしで駐車場に入れる)。開場を待ちきれないこちらの思いとは逆に、人っ子一人いない正面玄関に家人と陣取りシャッターの開くのを今か今かと待ちわびていたあの光景。9時半少し前に、警備のガードマンさんがキョトンとした顔をしてシャッターを開けに来られ、交わしたあの信じられない言葉「列ばれたひとは初めてですよ。」。 制限時間(駐車制限4時間!?)があるのも不思議であるが、その間に出会った観覧者のあの人数。閑散という言葉しか浮かばなかった。 桃山、桃山と呪文のように繰り返す現在の陶芸界。にも関わらず、今回のような展覧風景を目の当たりにした時、当時を凌駕する時代の息吹さえも感じることが出来なかった。改めて言うまでもないが、険しい道のりである。 裏腹に、展覧されている作品の圧倒的な内容と充実度。あれだけのものが一堂に会することの驚きと関係者の努力に本当に頭の下がる思いがした。 展覧の中でひときわ端正に佇んでいた黄伊羅保茶碗『橘』。鉄分の多い砂混じりの粗い土に品よくかかった黄釉。ゆるやかな端反の口辺に、篦削りされた高台脇からやや広めの輪高台への一連の流れるような曲線。そしてなにより、桃山という時代のエネルギーを受け止めるだけの力を内包していた。 そして今、信水作の黄伊羅保茶碗に対峙している。彼自身に内包するうつわに対するエネルギーを表現した会心の一作である。うつわの持つエネルギーを受け止めるだけの時代が訪れる日を夢見て。 |
|
彼と始めて言葉を交わしたのはかれこれ3年前。壺屋での北村圭泉・上田光春二人展の折り、まだ本名の克明として各展覧会で実績を積み、いよいよ翌年の二代信水襲名を間近に控えたある寒い冬の日だった。前々から彼とは何時か一緒に歩みたいと思っていた。古丹波を深く研究し、茶陶界においても将来を嘱望されている人物。その茶入に関しては、すでに丹波に市野ありといわれる までの作品を産んでいた。 そんな彼が、ふらっと現れたあの日。店主と交わした言葉は二言三言。聞きしにまさるシャイな彼の態度は、その場に居合わせた主役のおふたかたとはまた違った空気感を持ち合わせていた。ただ、交わされた3人の陶芸談義は真剣そのもので、その内容と各々の研究の深さは、今でも鮮明に記憶しているほどのものであった。もちろん、あっという間に彼を好きになってしまったのは言うまでもない。 あれから3年。ようやく雪がとけ始めた。この冬の雅楽香コレクション「上田ひろみ仕覆展」で壺屋に初出品される彼の作品はもちろん茶入。それも20数年前に丹波の山で見つけた一塊りの土から生み出された作品。この夏にふと、試作がてら焼いてみたという徳利とぐい呑は、古丹波を彷彿させる出来。 即座にその土での茶入の制作を頼み込み出来上がってきたのが今回の掲載作品である。 上田光春氏とは同い年。互いの丹波での修業時代からその交流は続いていると聞いている。それぞれが丹波と信楽の茶陶界を背負って立つ存在になりつつある現在、光春氏の奥様の仕覆展が壺屋でのデビューというのも何かの縁。またひとり楽しみな陶芸家の作品が壺屋にやって来る。 |