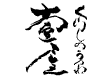|
|||||||||||||||
|
あれから2年が経とうとしている。一昨年、会期直前まで個展に向けてがむしゃらに取り組んでいた黄瀬戸。「各務賢周とゆかりの人々展」と内容を変え、9日間の会期中にご来場いただいた方々からの数々のお言葉が沁みているはずである。 |
|
自身初の関西での個展から丸3年が経とうとしている。彼のこの欄の更新もその時のままである。2年前の父・周海氏の突然の事故死をはじめ、この間に彼の身に降りかかった出来事の数々は、言語に尽くしがたいものがある。なにかのご縁か、そんな彼を傍らでずっと見続けてきた。 |
 |
 |
||
|
今春に「二人展」を予定していた。昨年暮れ、一方の雄が突然敵前逃亡を図った。事情がどうであれ、何の説明もなく約束を反故にする行為が人の道に反するということは自明の理である。そんな事情もあって、1ヶ月ほど時間をずらせての個展がまもなく始まる。 彼にとって壺屋での個展は、自身の予期せぬ出来事。まさに瓢箪から駒の如くに持ち上がった話である。そして、その個展に向けてのDMを作成するにあたり彼と打合せを重ねる中で、ひとつの試みをしてみたくなった。モノクロで轆轤を回す彼の手をメインに据えたDMの制作である。従来の、個展用に作りためた作品の中から選りすぐりを選びDMを仕上げるという手法を、どうしても今回は採用したくなかった。否、採用することが出来なかった。 今回、個展へと発展させざるを得なかった過程における彼の態度を見ていると、そこには実に若者らしい清々しく真摯な姿があった。そして、やるからにはと、従来の自分を超えるべく新たな取り組みをするという。3回分の窯を焚けるだけの作品をまず作り貯め、連続3回の窯焚きに挑み作品を出してくるという。 本来なら、延期あるいは中止にすべき事態である。にもかかわらず、終始一貫彼は二人展の相手であった作り手のことを思いやり、さらに自身が可能な限りの努力と創意工夫によって個展へと昇華させるべくこの期間を過ごしている。そんな彼の「手」に敬意の念の意味を込めて、今回のDMを作ってみようと思った。何故3回連続窯を焚くことにしたのですか?との私の問いに、彼は『窯を続けて焚くことによって、今まで以上のガス窯による黄瀬戸の「焼き」の可能性に迫りたいのです。』と言った。関西での自身始めての個展に対する彼の姿勢には、物事に対して真正面からぶつかっていくという、若者が本来持っている無限の可能性を引き出すパワーを感じる。大いに応援すべき心意気である。 DM用の「手」の撮影を終え、帰り支度をしながら最後に、今回の作品の作り(轆轤)について尋ねてみた。彼の答えは一言『これでも、轆轤20年以上廻してますから』。実に頼もしい若者の個展。楽しみである。 |
|
昨年秋、久しぶりに訪れた恵那の窯場で、彼は「一から黄瀬戸の釉薬を見直そうと思っているんです。」とつぶやいていた。父・周海氏とはまったく違った独自の釉薬で黄瀬戸に挑戦してきた10数年を振り返って、「一に戻る」必要性を噛み締めているその口ぶりに、作陶人生を振り返り何か期するものを感じている彼の姿がそこにあった。 あれから、半年が過ぎようとしていたある日、「珈琲碗を見て欲しい。」と1組のセットが送られてきた。焦げもなく、タンパンも冴えてはいない、しかしながら今までの油揚手の雰囲気とはあきらかに違う独特の油揚手がそこにはあった。さらに私を驚かせたのは、その造形である。 あるお客様から、黄瀬戸の珈琲碗を作って欲しいと頼まれて早3年以上の歳月が流れている。もちろん彼はその間に、何点もの試作を私に見せてくれていた。そのどれもに、その造形からくる印象が、洋食器のそれに勝るとも劣らないとまでは感じることが出来なかった。これは、彼以外が作る陶器の珈琲碗に共通する印象でもあった。陶器のあたたか味ややわらかさが、その「手」とともに全体の印象を重たくしている。よく言えば「民芸風」とでも表現すればいいのだろうか、そういう匂いが珈琲という飲み物と微妙な不協和音を奏でていると感じていた輩も多いのではないだろうか。 今回の珈琲碗、陶器独特のやわらかさは残しつつ、どこか上品な雰囲気がある。彼曰く「少し小さめにしたのは、とっておきの美味しい珈琲をゆっくり味わって頂きたいから・・・」と、飲む状況にまで心を砕いて作ったからかもしれない。 もちろん30歳すぎの彼が作る珈琲碗には、まだまだ熟達した雰囲気を醸し出せてはいないとは思う。ただ、彼が本来持っている内面の温かさが素直に表現され、気を衒ったところのないその造形は、『今夜は例のとっておきの豆でゆっくりとブラックコーヒーを』と思わせる。一に戻って何百いや何千という釉薬テストから始めたその取り組みは、彼を一回り大きくさせたように映る。来春に予定している二人展に向けて、いよいよその進化は加速し始めた。 |
|
| 先日、彼の手料理を馳走になる機会を得た。実に手早く、その味に至っては玄人裸足であった。その実を聞くと、窯焚きの時や家人が留守の折りは、もっぱ
ら彼がシェフで周海氏が大食漢のお客様となるようである。料理人にも憧れた時期がある彼の作り出す食器には、使ってみたくなる楽しさが潜んでいる。絵付けも好きだというだけあって、実に自由でバランスがいい。 中学を卒業して、父のもとで大いに学び・大いに遊び、20歳ころ数年は美濃の陶土を扱う会社で他人様の飯も喰ってきたという。そんな彼も30歳をすぎ一児の父となった今、初の親子展に向けて目の色が変わって来た。 この原稿を作っている5月下旬、所用で彼に電話を入れると「この期に及んで・・・もう一度土を作り直してます。」と笑っていた。実に彼らしい実直さである。外見は、最近の若者のそれと見まがう荒々しさを宿している。内実、非常に気持ちがやさしく、人に対する真摯な姿勢は実に爽やかで清々しいものを持っている。 彼には常々、料亭の食器と居酒屋の食器との違いを私なりに話をしてきた。どちらがいい悪いではない、もちろん高い安いでもない、長く大事に扱われるか粗雑に扱われるかの違い、料理が栄えるか栄えないかの違い、そして使い手に愛されるか愛されないかの違いを。結局は人が作り出すもの。作り手の心がそのまま素直に映る。料亭であれ居酒屋であれ、はたまた一般家庭であれ、使い続けられ愛され続ける食器をつくるのは至難の業である。彼には親子展が始まっても「この期に及んで・・・」といい続けてもらいたい。『あの各務周海の息子』という形容詞と一生付き合っていかなければならないのだから。 |
|
海も見えず、松原もなく、周辺からあがる炎もない。戦国時代には遠山の庄と呼ばれていた地で、ひとりの青年が取り組む唐津。毎回毎回訪れるたびに苦言を呈してきた遠山唐津。 父は言わずと知れた黄瀬戸の名手・各務周海。幼少の頃より父に連れられ、美濃・瀬戸の古窯研究に山中を歩き回っていたと聞き及んでいる。父をして「ヤツの食器は不思議と窯切れしないんや」と言わしめる独特のロクロ技術を持っている。そんな父子が恵那の山中で見つけたひとかたまりの土。即座に唐津に取り組むことを決意させたという。それから10年以上の歳月を費やして、彼が取り組む遠山唐津がようやくその真価を見せ始めた。 唐津焼には二つの顔がある。静けさと荒々しさ。上品さと豪快さ。この一見相反するように感じる二面性を上手くひとつの器の中で表現している作品が、現在の唐津焼には少ないと感じてきた。今回の彼の壺には、それがバランスよく表現出来ているように映る。 陶芸家の多くが表現しきれない品格のあるうつわ。今までは、おおらかで自由な発想から作品を生みだしてきた彼が、今秋に挑む壺屋での親子展に向けて変わり始めている。ロクロ技術・釉薬の研究・窯焚など様々な技術的習熟を必要とするこの世界にあって、人を磨くことの大切さを感じ始めている彼の今後の作品が楽しみである。 恵那で見つけたやっかいな土と灰釉の組み合わせ。若いからこそ挑戦できるものがある。決して遠回りではない、彼の歩んでいる道は父・周海氏が歩んできた道に他ならないからである。賢周作品は彼自身でしか作り出せない。 |