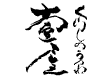|
|||||||||||||||

信州松本、春の芽吹きを五感で感じられるこの季節にここ数年毎年訪れている。還暦を超えた御年になられてから、さらに精力的にやきものを研究しておられる御仁に会いに。若いころから嫌というほど釉薬の研究に没頭し、爪の間から入った釉薬の原料で金属アレルギーにまでなって到達した境地になお満足などされていない。 壺屋での3回目の個展(2012年)が終わった翌年から『もう一度、金属の元素から勉強し直してみようと思って。』と、信州大学の社会人枠を活用し理学部の門を叩かれた。文科系出身の店主にはチンプンカンプンの元素記号の説明を、講義で写し取ったノート片手に説明してくださる姿は、科学少年のように輝き本当に楽しそうである。 やきものが元来持つ二面性。焼成による化学変化に裏打ちされた釉調と、人の指先によって生み出される形状。綿密な化学式の存在と、経験の上に積み上げられた勘。 その表裏一体の一見パラドックスに見える世界も、突き詰めると修練と積み上げのための時間軸の不足に帰結するように、彼の姿を拝見するにつけ感じる。 『もう少し、待っといて!って皆さんに謝っといて。』と、また今年もあの笑顔で言っておられた。皆様、本当にお待たせしています。松林さんは元気です! |
|
信州の春の息吹は軽やかである。 近代建築に生まれ変わった松本駅舎からは、透き通るようなどこまでも続く青空、雪解けを待つ中央アルプスの峰々、そしてその青と白をがっちりと受け止める大地の黒が、芽吹き始めた新緑と春霞の向こうに現れた。 あれから丸6年が過ぎた。「青瓷の展開」と題し科学的な考察を加えた、非常に意義深い展覧会を開催してから。還暦を前後し、いよいよその円熟味を増した作品の創造を、と次回展に意欲を燃やしておられた矢先の体調の変化。ご本人にとっても松林作品のファンにとっても長い時間の経過であった。 春の信州とはいえ、日中は関西と変わらないほどその日は暑かった。松本駅からご自宅を訪ねる道すがら、様々な思いが頭をよぎる。いつもの一間に通された瞬間、その様々な思いは春霞の彼方へと消え果てた。先ほど降り立った松本駅舎から見た風景が、その空間に広がっていた。 今までにない貫入の景色を抱いた信州の空を思わせる青瓷。前回展の青白い月白とは全く異なる淡雪の如き白瓷。そしてそのコントラストをがっちり受け止める大地のような漆黒の天目。6年という時の流れが、決して無駄でも遠回りでもなかったことを、うつわたちは語っていた。 訪問を終え、すっかり夕刻をむかえていた県の森を通りかかると、日中とは打って変わって、我が興奮を冷ますには十二分な冷気を含んでいた。 壺屋で3回目となる本展。今まで以上に楽しみが膨らんでいる。 |
|
『青瓷の展開』と銘打った展覧会を2006年6月24日から開催する。 磁器の起源は、さまざまな見解があって定まっていないのが現状である。それには、何をもって磁器とみなすかの判断基準が一律ではないからといわれている。これは「青磁」と「青瓷」の明確な違いを示す基準がないのもひとつの原因にほかならない。「瓷器」(一般的に半磁器と呼ばれる素地・胎土に若干の鉄分が含まれた吸水性のある焼物)の概念で「せいじ」を捉えた場合、青瓷の起源は後漢中期に遡り2000年近くの歴史が存在することになる。 そして、青瓷を灰釉(カイユウ)を用いて器面にガラス質の層を作り出した焼物という概念で捉えたとき、興味を引かれるのがその色の違いと変遷である。創成期の後漢中期から呉・晋の時代にかけての青瓷は、灰褐色や暗褐色をなす透明度の低い色調である。その後、南北朝時代を経て唐の時代に入ると、越州窯を中心に青や緑に透明感が加わりなめらかな質感となる。そして、宋時代とともに中国陶磁史上の黄金期が始まり、耀州窯のオリーブグリーンの輝き、汝窯の瑪瑙(メノウ)にもたとえられる上品な失透気味の淡い青色、鈞窯では澱青釉と呼ばれる失透性の青色を呈した「天青」そして月の光のような輝きの「月白」と呼ばれる色を生み出す。また、唐時代に入ると全盛を誇った越州窯は衰退し、江南地方にはいよいよ龍泉窯が「玉」とも称される完成度の高い粉青色とともに全盛期を迎える。その後、南宋時代に入ると日本でもなじみの深い「珠光青磁」や「米色青瓷」が現れ、「紫口鉄足」と呼ばれる鉄分が多い灰黒色を呈した陶器質で貫入の多い日本人好みの青瓷の完成を見る。 このように、青瓷を色で捉えるとその歴史的変遷が興味深く、松林氏に色を中心においた青瓷の展覧会が開催できないものかと持ちかけた。彼からは二つ返事で了承を得、『青瓷の展開』というタイトルで日の目を見ることになった。今回の展覧会は、松林作品のほかに、作品の解説と古窯の陶片、さらに顕微鏡による科学的分析と考察を加えたものになる予定である。 単なる作品の展示即売を超えた展覧会の開催。天井桟敷の住人たちの微笑と、今までの経験の集大成から生み出される松林作品の完成度を思い浮かべたとき、またひとつ壺屋の伝説になる展覧会が始まろうとしている。 |
|
||||||||||||||||||
昨年(2003年)12月、3テーマ3期間というとんでもない展覧会を開催した。正直、しばらくはこのような企画展はしたくないとの思いがあった。それほどまでに熱気と活気に溢れ、逆に言えば消耗しきった展覧会であった。今振り返ってみると、テーマを決めたことによるプレッシャーとの闘いの中、上田光春氏が発表してきた作品は出色の出来で、そのことが展覧会の成功の第一要因であったと感じていた。 |
|
今年(2002年)の晩秋、壺屋4周年を記念した二人展にと製作された水指である。四方を角切りし輪花を思わせるその造形をはじめて見たとき、彼の確かな歩みと凄まじい研究のあとを感じた。 数年前ある雑誌で、松林氏に対して「破調」を求めた記事を読んだことがある。あまりにも端正な茶陶をつくる彼は、時として作家としての彼の本質を隠してしまうのかも知れない。 「昔の名品の完成度は、轆轤・釉調などとは別の次元にあるように最近感じ始めているんです。」と彼は言う。また、今回の二人展の最終打ち合わせでの小宴の折りに、彼は近年、陶芸家とは違うものづくりに触れる機会を出来る限り増やしていると言っていた。刀匠・木地師などとの触れ合いが、彼の作品に幅と膨らみをくわえ始めている。 そして出来上がってきた水指。明らかに数年前の作品とは違う、ゆったりとした奥行きを感じる。あえて今回の二人展には、茶陶を中心に作品をお願いしている。必ず見えてくるはずである、彼の目指している次元が、そして確実な歩みが。ただの写しではない、本物の本質を捉えた歩み。この歩みこそが彼の「破調」である。 もちろん、蓋は二人展のもうひとりの主役である宮原省二の作であるのは言うまでもない。 |
|
「雨過天青」(雨上がりの空の色)。青瓷の青の喩として、しばしば用いられる。龍泉窯の『馬蝗絆』(東京国立博物館蔵・青磁輪花碗)や『万声』(久保惣記念美術館蔵・青磁鳳凰耳瓶)に代表されるその青も確かに美しい。 一方、汝窯・南宋官窯の青は、その歴史とともに実に謎めいた青である。明るい粉青色の神秘的な美しさは、その姿形と相まって気品が漂う。そんな青瓷に憧れていた。 あるギャラリーの個展で神秘的なそんな青瓷と出会った。西岡小十に惹かれ、唐津に魅せられていたあの頃、ふと目にしたのが松林青瓷であった。それ以来、何となく青瓷の湯呑を集めるようになっていた。十数名の青瓷作家の湯呑が集まりそれなりに楽しんでいた。あの震災の日までは。 陶片と化したうつわたちを整理していたある日、圧倒的な完成度の青瓷片が目に止まった。胎土・釉薬ともに青瓷の命ともいうべき均一さが図抜けていた。早速、かき集めてみると一つの湯呑が出来上がった。そう、松林青瓷である。 それから5年。憧れでしかなかった松林青瓷。いずれは・・・との思いは持っていた。そんな2000年夏。宮原省二(木曽漆器)に、「俺の高校の一年上で信州松本でいい青瓷をつくるのがいるから」と紹介されたのが、何と松林廣であった。 それから約10ヶ月が過ぎた。彼のホームページの最初の作品は、花器と決めていた。彼の作り出す花器の姿形は、端正で上品である。そして、憧れていたその神秘的な青と相まって気品すら漂う。そして期待どおり、たっぷりと時間をかけて見事な作品を仕上げてきた。もちろん既存の作家の作品とのハーモニーも抜群である。出会いから十数年。時間はかかったが、そんな青瓷が並んでいる。 |