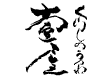|
|||||||||||||||
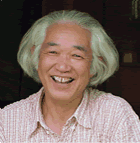 |
何から書き始めればよいのか、未だに整理がついていない。 亡くなる2週間前。いつものように家人と永田にある窯場を訪れた。あの、なんとも人懐っこい笑顔でその日も迎えて下さった。黄瀬戸・志野・織部はもちろんのこと、いつもの事ながら話題は政治経済から四方山話にまでおよぶ。話題が尽きない中、築窯中の窯の話になると、いてもたっても居れないとばかりに「時間あるか?今から岩村へ行こう!」とそそくさと身支度を始められた。これもいつもの周海さんだ。 |
|
5月22日。その訃報は飛び込んできた。前日に箱書きされたという作品達が到着し、そのお礼も兼ねて連絡をと、周海さんの携帯に連絡しても繋がらない。そんな時に、あるお客様からその知らせは舞込んだ。「昨日、周海さん交通事故で亡くなったのか?」と。 |
|
窯は亡くなる前日にほぼ完成し、これからその窯で生みだすはずであった織部の試作品が存在する。絶筆となった銘「春乃風」の黄瀬戸茶碗とともに。これは周海さんが、子息に『あとは。よろしく。』とあの笑顔で、春の風の如く逝かれた証しであろうか。 |
|
四十九日も過ぎ、改めて、以前HP掲載のためにとお願いした写真を眺めている。 |
|
あれから2年半の歳月が流れた。あの各務親子展から。 加藤唐九郎が挑み続けた「黄瀬戸」、荒川豊蔵が人間国宝に認定された「志野」。何故かあの地方には、このふたりの名前がついて回る。そしてこのふたりが挑み続けた「桃山」という「亡霊」が呪縛のように絡みつき、「伝統」という呪文がさらに今を難しくしている。 周海氏に『桃山とは』と問いかけたことがある。彼の答えは明確で、『エネルギーのあった時代』との一言であった。それは作り手にも使い手にも、さらにはそれを扱っていたであろう我々のような人間にも。つまりは、その爆発的なエネルギーの結晶として、今日いわれる「桃山陶」が形成されたと彼は考えている。だからこそ、その呪縛にとらわれている現代陶芸界を見渡した時、無冠無所属であるにもかかわらずこれほどまでに人々を魅了する各務周海とうい陶芸家の異彩が、嬉々として輝いているのも頷けるのである。 周海氏のエネルギー。それは、作ることに対する貪欲さにほかならない。『恵那山中で見たことのないような良質の天然風化長石見つけたんや。これを釉薬にして志野を作ってみたいと思ってるんや。』と語る口調は、まさに作ることの喜びや楽しさに溢れていた。そこには、「桃山」だの「伝統」だの、さらには認められたいだの儲かるだのというフレーズは介在しない。その純粋な、作りたい、どんなものになるのだろう、という想いが周海氏の強烈なエネルギーを生み出す源になっているのだと感じた。 6月下旬(2007年)に予定している壺屋での初個展では、完成度を増した「黄瀬戸」にくわえ、この「志野」も登場する予定である。緑寿をすぎ、さらにエネルギッシュな彼の姿を見ていると、「桃山」という時代の本物のものづくりの姿がだぶる。 |
|
この秋(2004年)壺屋で初親子展を開催する。そのタイトルも『各務周海・賢周の歩み』という壮大なものになった。この企画を持ち込んだあの日、周海氏はある決意をしたように感じた。 恵那の市街地から車で数十分、江戸時代には岩村城の城下町として栄えた「岩村本通り伝統的建造物群保存地区」の一角にある旧商家の建物に私は案内された。敷地内に疎水が流れ脇には梅の古木が立つ、その歴史を感じさせる空間に作品達は眠っていた。 1985年作の伊賀掛花入に始まり、89年の志野菖蒲文皿、93年の鼠志野鉢、95年の志野水指、02年の志野茶碗、そして同時期に作られた黄瀬戸の茶入・水指・茶碗そして鉢・皿・徳利・ぐい呑。その中には、東京都庭園美術館で昨年開催された『現代日本の陶芸・受容と発信』で出品された今回掲載の黄瀬戸水指を始め、過去に雑誌・取材などで取り上げられた作品群が含まれていた。どの作品も見ている私を圧倒し、『歩み』というタイトルを待っていたかのようにその歴史ある建物の中で、ゆっくりと眠りから覚めたのである。周海氏は、今までの自分のすべてを見せようとしている。これは、父から息子へのメッセージに他ならない。かれこれ15年、同じ窯場で向き合って来た親子。共に古窯跡を巡り、土を探し、多くを語り、薫陶も数限りなくしてきたであろう。それだけでは伝えきれない何かを今回は見せようとしている。ある意味、最初で最後。また楽しみな展覧会が壺屋にやってくる。 |
|
伊賀焼の歴史は複雑である。大きく二つの時代が存在する。秀吉・利休時代の筒井家(順慶亡き後の定次の時代)が指導製作したとされる筒井伊賀。そして遠州時代のほんの7〜8年だけ作品が製作されたといわれている藤堂家(虎高・高虎時代)が開花させた藤堂伊賀。以降の歴史ははっきりしない。焼締花入の世界でよく耳にする言葉に『伊賀に耳あり、信楽に耳なし』というのがある。現在では『筒井伊賀に耳なし。藤堂伊賀に耳あり。』というのが一般化しつつある。耳ひとつでも、様々な論争が巻き起こる和物花入の王様・伊賀花入。現存する古伊賀花入の数の少なさもひとつの要因であるが、何よりもその完成された美しさによるところが大きい。陶工たちのロクロ技術の高さもさることながら、器肌に現れた緋色・焦げ・ビードロの絶妙なバランスが命とも言える。これは何度も窯に入れ、焼締めていく課程でしか生まれないものである。つまり、それだけ手間のかかる代物である。 この伊賀花入を長年にわたり深く研究し、独自の高いロクロ技術で昇華させて生まれたのが、今回紹介する『遠山伊賀花入』である。そのフォルムと独特のビードロとかせ肌は恵那山麓の旧「遠山の庄」の土と窯で生まれ、そのことから命名された。この秋(2004年)壺屋での親子展で初展覧されるこの花入にかける作家の思いは、伊賀風の焼締作品を作り始めてから20数年という歳月の流れにも読みとれる。じっくり作り込んだ作品。まさに圧巻である。 |
|
美濃陶にとって「志野茶碗」という響きには特別なものがあるように感じる。国宝和物茶碗二作のうちの一作は言わずと知れた志野茶碗『卯花墻』。そしてその歴史は、天正時代にまで遡る。日本独特の「白」の表現を長石単味の白釉と百草土という特有の土を素地に半筒型の茶碗で表現した。 この茶碗を400年以上、数限りない陶工が連綿と作り続けてきた不思議。「黒」を代表する『楽茶碗』とは、対照的な歩みである。 それは日本人の価値観から来るものではなかったかと思う。柔らかな包み込むような暖かな「白」を好む。いや、好んできたのではないか。そんな歴史が、多くの「志野」を生み育ててきた。ただ、今の「志野」は少し違うように感じる。 陶工が、陶芸家と名前を変えた現在。「白」の価値観も多様化していると人は言う。「志野」を表現手段と言い切る陶芸家も少なくない。反比例するかのように、手元で愛でたい「志野」は減っていると感じているのは私だけではあるまい。 各務周海が創る「志野」。胴の轆轤目が力強く現れ、筍を思わせる鉄絵のバランスと雄大な山路にぼんやりと浮かぶ緋色、そしてなにより「白」の美しさ。ゆっくりとじっくりと育てていきたい「志野茶碗」である。 |
|
左党垂涎の的である桃山の「黄瀬戸六角盃」。ぐいのみ手の本歌として、そのとろりとした艶がコレクターを魅了し、「いつかは手に入れたい」と思わせる。 そんな黄瀬戸六角盃の世界に、独自の表現の作品を送り込んできた。やや小ぶりであるが、角の鋭さ・力強さとも申し分なく、高台も実に丁寧に削り出している。また縦方向に箆で線状痕を付け、正面に1箇所・見込みに1箇所、タンパンがあしらわれている。そして何といっても、黄瀬戸の第一人者としての名声を不動のものとしている独特の油揚手の雰囲気と、口辺と高台付近の焦げのバランスが絶妙である。 六角盃イコールぐいのみ手という従来の価値観を十二分に理解し、あえて油揚手で独自の世界を表現する彼の力量 と作品の完成度は、桃山第一主義の各輩をも一目置かせる存在といっても過言ではない。 |
|
20世紀最後の11月初旬、あの茶碗と再び出会える日の朝を迎えた。 恵那から望む南アルプスは雪化粧を終え、たち込めた朝霧は市街地を覆い、山々の稜線を一層くっきりと浮かび上がらせる早朝。 あれから3ヶ月、ようやくこの日がやってきた。後ろ髪を引かれる想いで帰途についたあの暑い夏の日。未だコレクターよろしく、手に入れそこなった作品に対する、初恋のような焦がれた想い。「どうしても、今は手元から離したくない。」と譲らなかった周海さんの凛とした眼差しに、それ以上言葉を継げなかったあの日。 あの茶碗とは、この掲載の『黄瀬戸茶碗』である。品のいいタンパンを中心に、油揚手とぐい呑手が、まるで灰釉を掛け分けたかのように表れ、油揚手の中に浮かび上がった焦げと箆目が何ともいい景色を与えている。「このぐい呑手の表情が、お手本なんだよね。」と油揚手の名手は次の目標(21世紀)をはっきりと脳裏に刻みあの日呟いていた。なんと見所の多い作品であろう。 実はこの茶碗は、7月にある雑誌に掲載されている。通常この手の作品は、作家の手許に残らない。現在の大多数のコレクターと言われる種族にとっては、格好の獲物である。ただし、掲載雑誌付きで。 恋焦がれたこの茶碗に、あの朝霧に浮かぶ南アルプスの稜線を想い帰途についた。ふと振り返ると、山々の稜線はぼんやりと何も語らず、ただこの茶碗に晩秋のやさしい光があたっていた。 |
|
岐阜県恵那市郊外の山懐。この地に窖窯を構えて30年が過ぎた。黄瀬戸と志野を焼きつづけている。その円熟味が増した黄瀬戸作品に魅せられた。 彼の黄瀬戸は、古田織部が愛し加藤唐九郎が挑んだ「油揚手(アブラゲデ)」と言われる鈍い光沢の釉肌に、品のいい「胆礬(タンパン)」と言われる硫酸第二銅(板緑青)の景色。窖窯で100時間超じっくり焼成された「焦げ」がその景色にアクセントを与え、桃山期の黄瀬戸に迫る作品である。 黄瀬戸は、その釉肌によって時代と好みが分かれる。利休が好んだという、艶やかな「ぐい呑手」。織部の時代を中心に「朝比奈」という名碗を生んだ「油揚手・あやめ手」。江戸期に見られる、黄瀬戸の雅を地に落とした光沢の強い「菊皿手」。 今回掲載の「黄瀬戸片口」は、〔黄瀬戸の周海〕の実力を如何なく発揮した秀作で、油揚手の釉肌に適度に見られる焦げが上品で、縦長の片口の中心部から菖蒲を連想させる草文にタンパンが所々アクセントとなり、実にバランスよく仕上がっている。本来の酒器として使うもよし、たまには野の花を投げ入れるもよし、また夏にはビールをグイッといくもよし。 帰り際にひとこと、「これだけの作品の箱書き、黄瀬戸片口酒器と書くより、黄瀬戸片口と書いていただけないでしょうか?」と言ってみた。「そらエエ!」と即座に答えがかえってきた。型にはまらず、笑顔のやさしい陶芸家にまた一人出会えた。 |