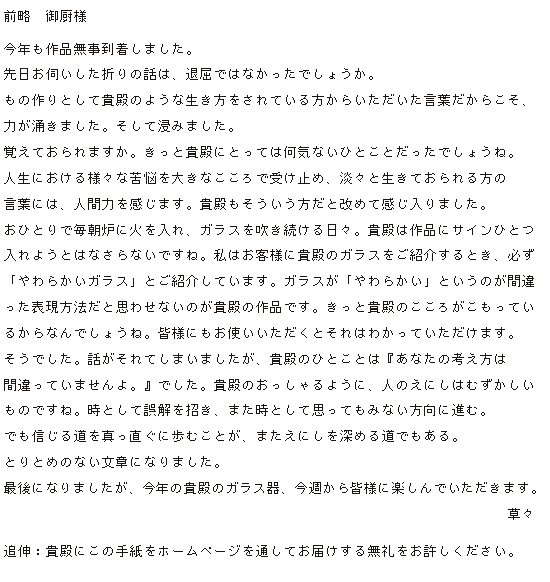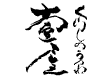デカンタージュあるいはデカンテーションなどと呼ばれるワインでのお作法。ご節丁寧に、この項で知ったかぶりしてつらつらと解説するつもりは毛頭ない。また、生憎そこまでの知識も経験も有してはいない。
日本の食文化にワインやウイスキーが本格的に入ってきて約100年といわれている。それまでの我が国は、一部地域的に脈々と受け継がれてきた焼酎を中心とした蒸留酒文化を有するものの、やはり醸造酒の王様日本酒が食文化の中心にあったことは異論をはさむ余地のないところであろう。また、その日本酒文化の歴史が、我が国のうつわの歴史にも多大なる影響を及ぼし続けている事実も今更つらつらと述べるべきものでもない。一方、洋酒と呼ばれる酒文化とともに入ってきた洋食文化の潮流は、我が国に和食器や洋食器などという言葉や区分を生み、ガラス器文化を花開かせた側面を有するという、実に興味深い側面を垣間見せる。
こと酒器に限定して考えたときに、この興味深さは不思議へと変化する。つまり日本酒を中心と考えたとき、日本人は和食器と呼ばれるジャンルに徳利というある種のデカンタを有し、盃やぐい呑という酒器を有する。一方、洋酒という側面から日本人の好む酒器を俯瞰すると、多くの場合デカンタなどという代物は用いず、ガラス器という酒器のみで酒宴を楽しんでいる。この不思議さはどこから来るのであろうか、長年その答えを探し続けている店主であるが、今回掲載の御厨ガラスのデカンタを眺めていて、出口が少し見えてきた気がする。
ワインボトルやウイスキーボトル、あるいは本来は製造元を特定するためのラベルに、洋風文化の香りを敏感に感じてとってきた我が国のここ100年の西欧化の美意識。本来日本人が持ち合わせている、次元の高いうつわ文化の美意識を目覚めさせる御厨デカンタの存在は頼もしい限りである。 |